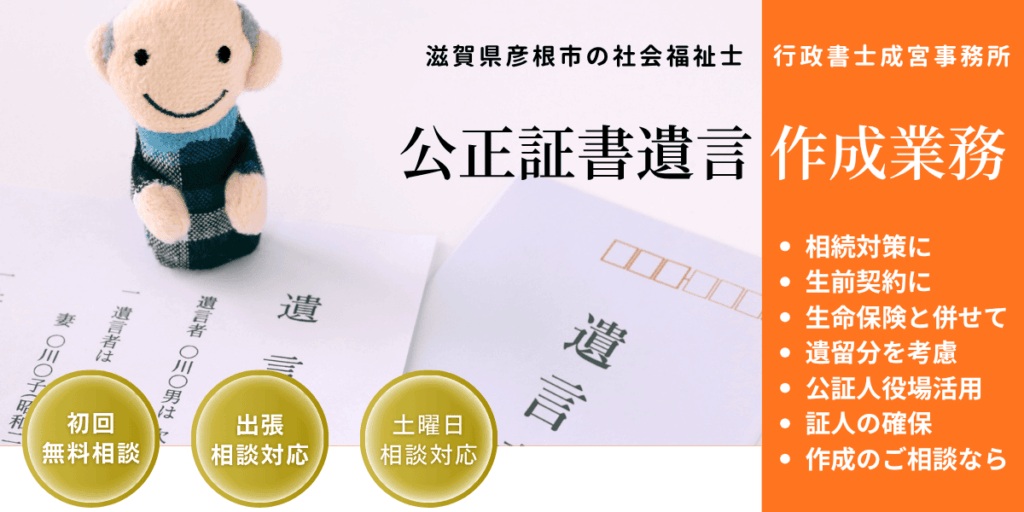
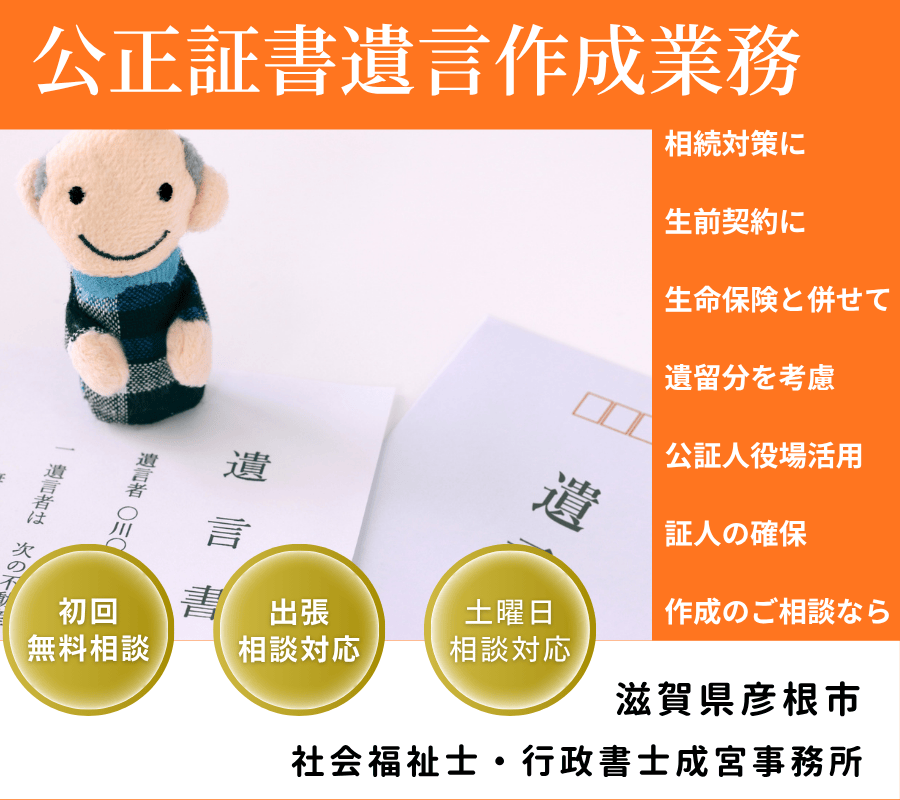
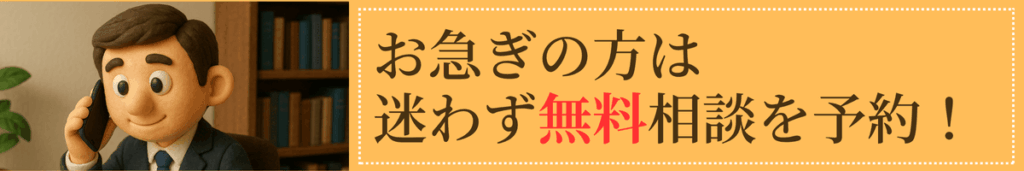
当事務所の公正証書遺言の作成業務について
公正証書遺言作成のための業務内容
公正証書は公証人が関与して遺言書を作成します。確実性という点で言えば、一番確実性の高い遺言の方式です。当事務所では次のような内容の業務を行います。
- しっかりと話しを聞いて遺言書の原案を作成します。
- 公証人と打ち合わせを行い、資料を提供します。
- 公正証書遺言の作成に必要な証人2名を準備いたします。
- 公証役場等で遺言書を作成します。
当事務所の業務報酬
当事務所の遺言書作成業務の報酬規定です。できるだけ計算しやすくしております。
| 遺言書作成業務 | 報酬規定 |
|---|---|
| 遺言書の原案作成(A4 1枚程度で書けるもの) | 22,000円【全国対応】 |
| 遺言書の原案作成(A4 2枚程度で書けるもの) | 44,000円【全国対応】 |
| 遺言書の原案作成(上記より複雑なもの) | 66,000円 |
| 自筆証書保管手続きの利用支援 | 11,000円 |
| 公正証書遺言の利用サポート | 22,000円 公証人費用が掛かります |
| 証人就任2人 | 22,000円 |
| 遺言執行者への就任 | 275,000円+ 相続財産 ✕ 1.0% |
※別途、郵送費、手数料などの実費がかかります。
公証人費用について
下記の公証人手数料と証人費用が自筆証書遺言よりも高くなる要因です。参考費用ですので、必ず事前に費用を確認します。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 |
| 10億円を超える額 | 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
①財産の相続または遺贈を受ける人ごとに財産の価額を算出し、上記の手数料を計算する。
②全体の財産が1億円以下なら11,000円を加算する。
③公証人が出張した場合は金額1.5倍になる。
ご相談予約からご依頼完了までの流れ
ここでは、当事務所への「相談予約→相談→業務提供→完了」までの流れについて説明させていただきます。
下記のとおり、お電話・メールフォーム・公式ライン・インスタグラムなどの方法を活用して相談予約をお願いします。基本的に、次のような内容をお知らせいただければと思います。
お名前:
相談予約日時(候補日を2つ程度):
相談希望場所:事務所・自宅など
電話番号・メールアドレス:
ご相談、お問い合わせなどの内容:
相談場所は事務所、お客様の自宅、ご指定の喫茶店等で相談を行います。(事務所以外の場合は出張費がかかります)
初回無料相談で、ご相談者様の抱える問題・課題などを共有し、可能であれば、解決策などのご提案をさせていただきます。この段階で、提供できる業務内容や、それにかかる費用などの大まかな提示をさせていただけます。
初回の相談を受けまして、問題点の解決に向けたロードマップとお見積を提示させていただきます。そのうえで、ご依頼いただける場合は業務契約を頂くことになります。
ただし、非常にお急ぎの場合で、依頼内容がシンプルな場合は、このSTEPを短縮させていただき、業務速度を重視した対応をさせていただきます。
契約後は、ロードマップの内容に則り、できるだけ早期に業務完了できる事を目指します。長期にかかる依頼も多いため、必要な場合には進捗報告なども行います。
ご依頼が完了したら、完了後の書類、お預かり資料などを返却いたします。この際に請求書をお渡ししますので、後日お支払いください。遠方の場合はレターパックなどでの返却にも対応します。
当事務所の特徴・安心して相談できるように
サービスの特徴について
当事務所では、社会福祉士の福祉の視点、ファイナンシャルプランナーのお金の視点、行政書士の法律の視点から、トータルな相談に乗ることが可能です。特に、ライフプランに関わる相談として、生前契約や相続対策、入管等の分野で強みを持つと思います。
相談前に、①依頼前提での相談にするか?②ただ相談するだけにするか?を確認するようにしております。また、相談やカウンセリングを得意とする社会福祉士資格の活用で、どのような内容でも気楽にご相談いただくことが可能です。
動けない方には出張相談を実施しております。また、平日にどうしても時間が取れない方のために土曜日も相談対応をさせていただきます。もちろん、初回相談は無料です。
(出張相談には出張料が必要となります。移動範囲30分程度で2,000円です)
司法書士事務所・税理士事務所等と提携しておりますので、色々なご依頼に対して、当事務所を窓口として連携したサービスを提供いたします。
基本的に、お客様の問題点の解決までの道のりをロードマップ(業務フロー)としてお知らせするようにします。併せて費用のお見積りを提示する事で、内容・時間・費用をご確認のうえ、業務のご依頼が可能です。(お急ぎの場合は、割愛させていただくことも可能です)
事務所の特徴・所在
| 事務所名 | 行政書士・社会福祉士・FP成宮事務所 | |
| 資格者名 | 成宮隆行 | |
| 保有資格 | 社会福祉士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士・宅地建物取引士・合気道6段 道場サイト | |
| 営業時間 | 月曜日から土曜日 9時~18時 予約をお願いします。 | |
| 事務所地 | 滋賀県彦根市平田町578番地6 | |


公正証書遺言の解説
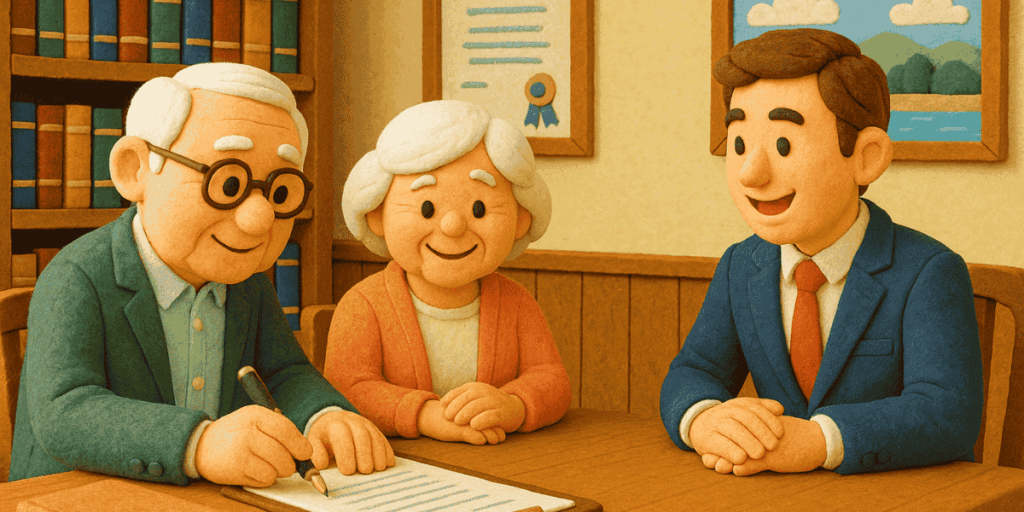
公正証書遺言は、遺言の形式の一つで、公証人という専門家が関与して作成する法的な文書です。民法969条に基づき、遺言者の意思が正確に反映され、形式や内容が法的に適切であることが保証されます。
主な特徴
- 法的効力が強い:適切な手続きで作成されるため、無効になるリスクが低い。
- 安全性:内容が公証人によって確認・保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
- 信頼性:遺言の内容が正確に伝わり、遺族間のトラブルを未然に防げます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、他の遺言形式に比べて多くのメリットがあります。
- 法的な確実性
- 遺言内容が明確かつ正確であるため、遺言が争われる可能性を大幅に減らせます。
- 紛失や改ざんのリスクがない
- 公正証書遺言は公証役場で厳重に保管され、遺言者や遺族が紛失する心配がありません。
- 遺族間のトラブル防止
- 遺言内容が明確であるため、相続人間でのトラブルや不満を防ぎやすくなります。
- 高齢者や病気の方も安心
- 遺言者が文字を書けない場合でも、公証人が代理で作成します。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言を作成する際の具体的な流れを見ていきましょう。
- 戸籍謄本や住民票、財産目録、不動産登記簿謄本などを揃えます。
- 財産内容や相続人について事前に整理しておくことが大切です。
- 公証人と事前に相談し、必要な情報や証人を確認します。
- 証人として、利害関係のない2名を用意します(行政書士が証人を手配する場合もあります)。
- 公証人が遺言者の意思を聞き取り、遺言書を作成します。
- 遺言者と証人が署名・押印を行い、手続きが完了します。
公証役場で厳重に保管され、必要な際に遺族が確認できます。
公正証書遺言が効果的なケース
公正証書遺言は、特に以下のようなケースで有効です。
- 不動産や多額の財産がある場合
- 財産の分割方法を明確に記すことで、相続人間の争いを防ぎます。効力が確実に生じる公正証書遺言が有効です。
- 家族構成が複雑な場合
- 再婚や子供がいない場合など、法定相続分にとらわれない意思を伝えることができます。
- 遺産分割トラブルが予想される場合
- 明確な遺言内容により、相続人間の対立を回避できます。
- 遺言者が高齢や病気の場合
- 公証人が内容を確認しながら作成するため、信頼性が確保されます。
作成時の注意点
公正証書遺言を作成する際には、いくつか注意が必要です。
- 遺留分への配慮
- 法定相続人には最低限保証される遺留分があるため、これを無視するとトラブルになる可能性があります。
- 内容の明確化
- 誤解が生じないよう、財産や相続人に関する記載を正確に行います。
- 証人の選定
- 証人は利害関係のない人物である必要があり、信頼できる人を選びましょう。
- 定期的な見直し
- 家族構成や法律の変更に合わせて、遺言内容を見直すことが重要です。